
- 今の職場の退職金が他の職場と比べて少ないのか気になる
- 将来転職を考えたとき、薬剤師の退職金がいくらもらえるか知っておきたい
- 退職金制度は複雑なため、どう計算されるのかよくわからない
薬剤師として働いていても、自分の退職金がいくらもらえるか知らない方も多いはずです。職場によって退職金制度や金額が異なるため、将来に不安を感じるかもしれません。この記事では薬剤師の退職金の相場を職場別に解説し、退職金制度の種類や計算方法を紹介します。
記事を読めば、自分の退職金の目安がわかり、将来のライフプランやキャリアプランの設計に役立ちます。薬剤師の退職金の算出基準は職場や勤続年数、役職などです。就業規則で自分の職場の退職金制度を確認しましょう。
【職場別】薬剤師の退職金の相場

薬剤師の退職金の相場を、以下の職場別にまとめました。
- 調剤薬局・ドラッグストア
- 病院(公立、私立、国立)の退職金
- 製薬会社
調剤薬局・ドラッグストア
調剤薬局やドラッグストアの退職金は企業規模によって異なります。大手企業では独自の退職一時金制度や確定拠出年金を設けていることが多く、退職金は高額になる傾向です。
中小規模の薬局では退職金制度がない場合もあります。退職金制度があっても、中小企業退職金共済を利用することが多く、大手企業と比べて退職金額が少ない傾向です。
調剤薬局・ドラッグストアの勤続年数ごとの薬剤師の退職金相場は以下のとおりです。
- 勤続10年:50~200万円
- 勤続20年:200~500万円
- 定年退職:500~1,500万円
病院(公立、私立、国立)の退職金
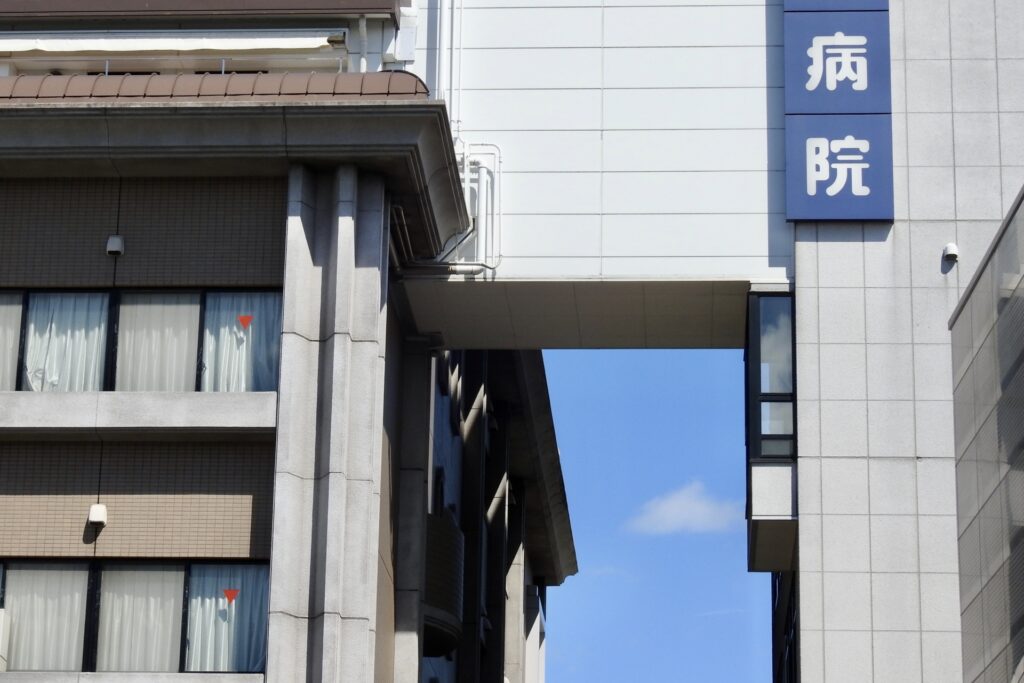
病院で働く薬剤師の退職金は経営母体によって異なります。公立病院や国立病院の退職金は公務員の規定に準じて計算され、勤続年数が長くなるほど高い退職金を受け取れることが特徴です。
私立病院の退職金は各法人が独自に定めたルールで決まり、退職金制度が存在しないこともあります。私立病院を希望するなら、入職前に就業規則などで退職金制度を確認しましょう。
製薬会社
製薬会社は企業規模が大きく、福利厚生が充実していることが多いため、退職金は他の職場に比べて高い傾向にあります。
製薬会社の退職金の目安は以下のとおりです。
- 大手製薬会社の定年退職時:2,000~2,500万円
- 勤続20年:1,000万円以上
多くの企業が退職金制度を「退職一時金」と「企業年金」を併用して導入しています。会社の業績や組織再編によっては、早期退職優遇制度が実施され、退職金が上乗せされるケースもあります。
ただし、中小企業やCSO(医薬品販売業務受託機関)では、大手企業ほどの退職金は期待できない点に注意が必要です。
薬剤師の退職金制度の種類

薬剤師の退職金制度の種類は以下のとおりです。
- 退職一時金制度
- 確定給付企業年金制度(DB)
- 企業型確定拠出年金制度(企業型DC)
- 中小企業退職金共済制度
退職一時金制度
退職一時金制度は退職時に会社から一括で支給される退職金の仕組みです。退職金の金額は「退職時の基本給 × 勤続年数に応じた支給率」で計算されることが一般的なため、長く勤めるほど退職金は増えます。
ただし、企業の業績不振や短期転職の場合は退職金が減額・不支給の可能性がある点に注意しましょう。勤務先の退職金の支給条件や計算方法は、就業規則や退職金規程で確認できます。
確定給付企業年金制度(DB)

確定給付企業年金制度(DB)は将来受け取れる年金が、あらかじめ決まっている企業年金制度です。企業が掛金の準備から資産運用まで行うため、自分で投資の知識を身に付ける必要がありません。元本保証されているため、確定給付企業年金制度は将来のライフプランが立てやすいメリットがあります。
退職金の受給方法は分割で受け取ることが基本ですが、勤務先によっては一括で受け取ることも可能です。会社の経営状況によっては、給付額が減る可能性があることを覚えておきましょう。
企業型確定拠出年金制度(企業型DC)
企業型確定拠出年金制度(企業型DC)は企業が拠出した掛金を従業員が運用し、退職金や年金を準備する制度です。企業型DCは運用成果によって退職金が変動します。
企業型DCには以下の特徴があります。
- 運用成績により受取額が変動し、元本割れリスクがある
- 掛金が所得控除の対象となるなど、税制優遇を受けられる
- 転職や退職時に資産をiDeCoなど他制度へ移換できる
- 原則60歳まで資産を引き出せない
企業によっては薬剤師自身が掛金を上乗せできる「マッチング拠出」制度を導入している場合があります。企業型DCは税制上のメリットもあるため、積極的に活用しましょう。
ただし、育児休業などで休職中は会社からの掛金の拠出が停止されることが多いため注意が必要です。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は中小企業が従業員の退職金を外部機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構)に積み立てる制度です。勤務先の業績が悪化したり、倒産したりしても、中小企業退職金共済制度では積み立てた退職金は必ず支給されます。
中小企業退職金共済制度のメリットは以下のとおりです。
- 掛金は全額会社が負担し、従業員の給与から差し引かれない
- 条件を満たせば、パートも加入できる
- 転職先でも、加入期間を引き継げる
ただし、加入してから1年未満で退職すると退職金は受け取れないため注意しましょう。
薬剤師の退職金の計算方法
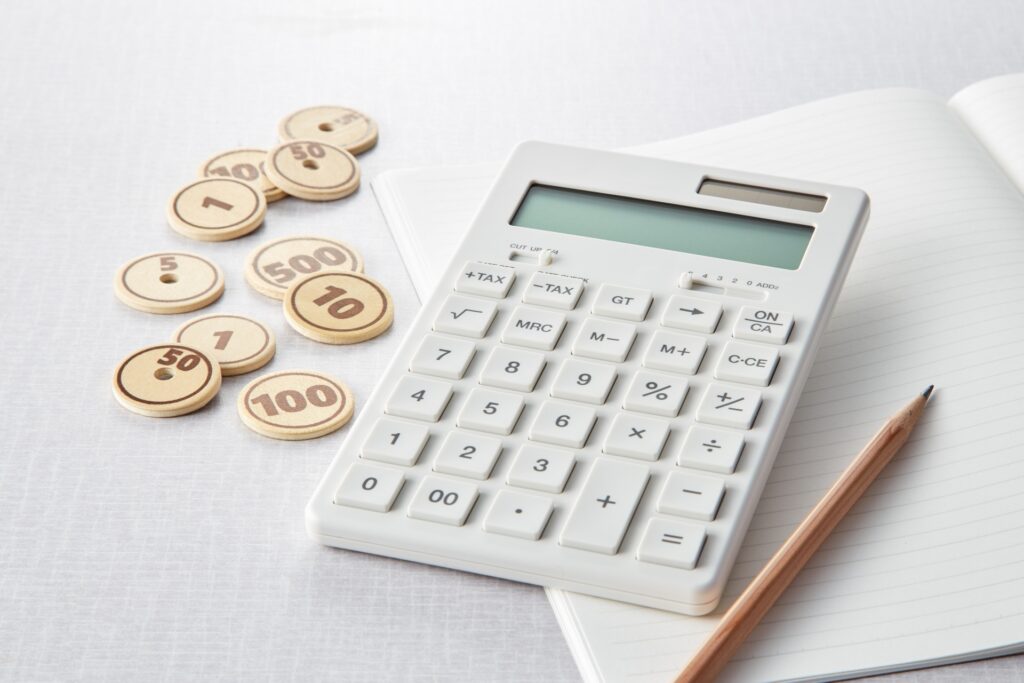
薬剤師の退職金の計算方法を以下の項目に分けて整理しました。
- 基本給にもとづく計算
- 勤続年数にもとづく計算
- 退職金計算の例
基本給にもとづく計算
退職時の基本給をもとに退職金を計算する方法は多くの企業で採用しています。基本給にもとづく計算方法は、以下の要素を掛け合わせて退職金を算出します。
- 退職時の基本給
- 勤続年数で決まる「支給率」
- 退職理由で変わる「退職理由別係数」
基本給にもとづく計算方法は、会社の就業規則や退職金規程を確認しましょう。
勤続年数にもとづく計算

薬剤師の勤続年数にもとづいて退職金を計算する方法もあります。勤続年数が長くなるほど、退職金の計算で使われる支給率が高くなることが一般的です。
勤続年数にもとづく計算方法は以下の式が用いられます。
- 勤続年数 × 定額
- 退職時の基本給 × 勤続年数別支給率
多くの企業では退職金を受け取るための最低勤続年数が定められているため、事前に確認しましょう。
退職金計算の例
実際に退職金がいくらもらえるか、実例を見てみましょう。自分の状況と照らし合わせると、受け取れる退職金をイメージしやすくなります。退職金は勤務年数や退職理由で変わることが一般的です。
モデルケースを以下に紹介します。
- 勤続3年・自己都合:約30万円
- 勤続5年・自己都合:約67万円
- 勤続10年・自己都合:約205万円
- 勤続10年・会社都合:約256万円
- 勤続20年・自己都合:約640万円
※上記の金額はあくまで一例であり、退職時の基本給や勤務先の規定によって変動します。
長く勤めるほど退職金は増える傾向です。同じ勤続10年でも、退職理由で退職金に差が出ることも覚えておきましょう。
薬剤師の退職金に影響を与える要因

薬剤師の退職金に影響を与える要因は以下のとおりです。
- 退職理由(自己都合か会社都合か)
- 役職や職種
退職理由(自己都合か会社都合か)
薬剤師の退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、退職金が変動します。自己都合退職と会社都合退職について以下に解説します。
- 自己都合退職
- 転職や結婚、出産や介護など、個人の都合で退職するケースです。自己都合退職は多くの企業で退職金が減額されます。
- 会社都合退職
- 会社の倒産やリストラ、事業所の閉鎖など、会社の都合で退職するケースです。会社都合退職は退職金が満額または割増で支払われることが一般的です。
会社都合の退職は自己都合よりも退職金が多い傾向です。退職理由の条件は勤務先の就業規則や退職金規程に記載されているため、退職前に確認しましょう。
役職や職種
役職手当がついたり、専門性の高い職種に就いたりすると、基本給が上がるため、薬剤師の退職金は役職や職種でも差が生じます。以下の役職や職種に就くと退職金が高くなります。
- 管理薬剤師・薬局長
- MR・研究開発職
パートやアルバイトの薬剤師は退職金制度の対象外であったり、正社員と比べて支給額が少なかったりします。
薬剤師が自分の退職金の現状を確認する方法3選

薬剤師が自分の退職金を確認するには、以下の3つの方法があります。
- 就業規則や労働契約書で確認する
- 会社の総務や人事に問い合わせる
- 会社外の情報源(厚労省など)で退職金制度を調べる
就業規則や労働契約書で確認する
自分の退職金を知る1つ目の方法は、就業規則や労働契約書を確認することです。多くの企業では退職金の支給条件や計算方法が書類に明記されています。
就業規則や労働契約書を確認する際は以下のポイントを押さえると、自分の退職金制度を正確に把握できます。
| 確認ポイント | チェック内容 |
| 退職金制度の有無 | 「退職金」「退職給付」などの項目があるか確認 |
| 退職金制度の種類 | 一時金方式か年金方式(DB・企業型DC)か確認 |
| 支給条件 | 最低勤続年数などの要件(例:勤続3年以上)を確認 |
| 計算方法 | 基本給や勤続年数、ポイント制など、金額算定基準を確認 |
| 退職理由の違い | 自己都合と会社都合で支給額に差があるか確認 |
| 関連規程の有無 | 就業規則とは別に「退職金規程」が存在するか確認 |
会社の総務や人事に問い合わせる

就業規則や労働契約書を読んでも退職金の詳細がわからない場合は、会社の総務や人事部に問い合わせましょう。産休や育休などの個人事情が退職金に影響するかどうかも総務や人事で確認できます。
ただし、質問の仕方は工夫が必要です。退職の意思があると誤解されないよう「今後のライフプランを考える参考にしたい」と伝えると、安心して対応してもらえます。
総務や人事に問い合わせる際は、以下の点を確認しましょう。
- 退職金制度の有無
- 退職金の種類
- 退職金の計算方法
- 産休・育休期間の取り扱い
退職金の詳細を直接聞きにくい場合や記録を残したい場合は、メールで問い合わせましょう。
会社外の情報源(厚労省など)で退職金制度を調べる
会社の就業規則や担当者に確認する以外に、厚生労働省が提供する情報でも退職金制度について調べられます。他の薬局や病院の退職金制度を知ると、自分の働き方や今後のキャリアを考える上での参考になります。
自分の会社以外で退職金を調べる方法は以下のとおりです。
- 厚生労働省の統計データで業界の平均を知る
- 中小企業の退職金制度を調べる
- ハローワークや労働組合を活用する
厚生労働省の統計データで業界の平均を知る

厚生労働省の「就労条件総合調査」では、医療・福祉業界全体の退職金の平均支給額や制度の導入率が公表されています。公的な統計データのため信頼性が高く、自分の職場の退職金制度と比較する際の目安になります。
厚生労働省の統計データを参考にして、薬剤師として働く職場を見直すきっかけにしましょう。
中小企業の退職金制度を調べる
中小企業の調剤薬局やドラッグストアでは、中小企業退職金共済(中退共)のウェブサイトが退職金制度の参考になります。中退共では退職金制度の仕組みや掛け金の金額、勤続年数に応じたモデル退職金額が公開されています。
ただし、すべての中小企業が中退共を必ず導入しているわけではないため、自分の会社の導入状況を確認しましょう。
ハローワークや労働組合を活用する
ハローワークの求人情報や労働組合を活用して、会社の退職金制度を確認しましょう。他社の退職金制度をチェックすると、自分の職場の退職金の目安になります。
ハローワークの薬剤師の求人票では「退職金制度あり」「退職金共済加入」などの記載を確認可能です。職場に労働組合があれば、業界全体の退職金水準や制度の実際について詳しく教えてもらえる場合があります。
薬剤師の退職金について知り、後悔しない人生設計を立てよう

薬剤師の退職金は勤務先の業種や勤続年数、退職理由によって変わります。調剤薬局やドラッグストアでは中退共を利用するケースが多く、大手企業ほど退職金は高額な傾向です。病院では公立・国立の退職金制度が手厚く、私立は法人ごとに差があります。
退職金制度は以下の4種類があります。
- 退職一時金制度
- 確定給付企業年金制度(DB)
- 企業型確定拠出年金制度(企業型DC)
- 中小企業退職金共済制度
退職理由が自己都合か会社都合かによって退職金の支給額は変わります。役職や職種によっても基本給が異なるため、退職金の金額にも差が生じます。
薬剤師として後悔しない人生を送るために、退職金について正しく理解し、早期からキャリアプランを立てましょう。退職金の有無や金額を知ると、将来の選択肢が明確になり、業務のモチベーション向上にもつながります。



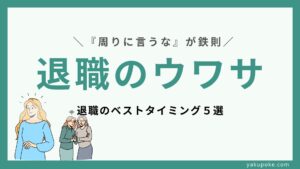


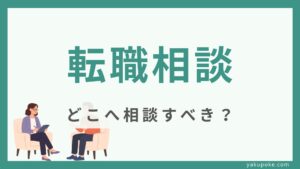
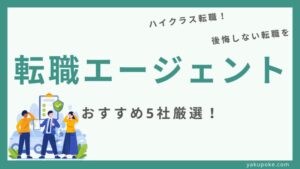

コメント