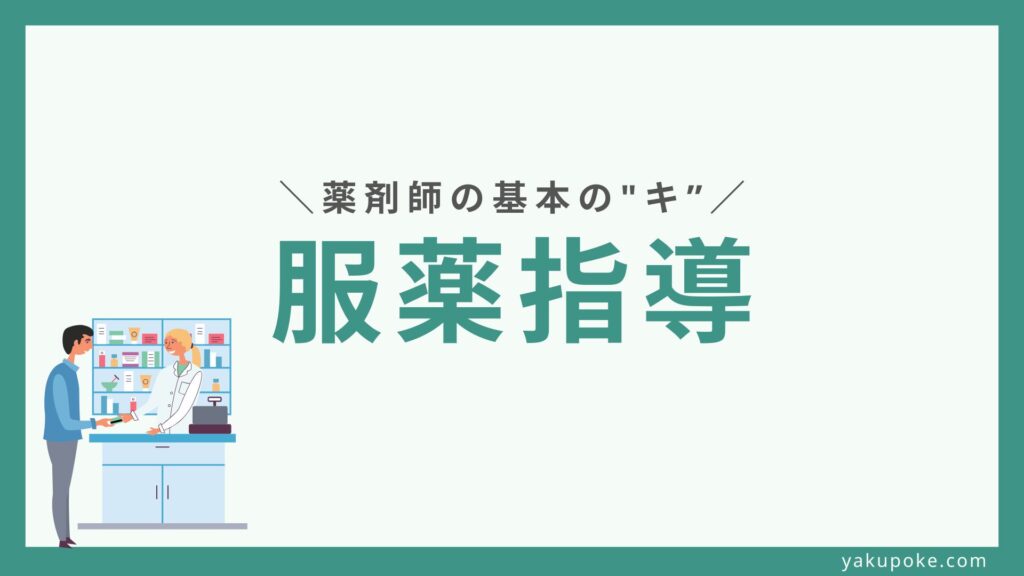
- 服薬指導では具体的に何を説明すれば良いのかな?
- 患者さん一人ひとりに合わせた指導ってどうすればいいんだろう?
- 服薬指導における注意点やトラブル回避のコツは?
薬剤師が患者さんに薬を渡す時、ただ薬を手渡すだけではありません。その瞬間には、患者さんの健康を守るための重要なコミュニケーションが始まっているのです。
患者さんが安心して薬を服用できるようにサポートする「服薬指導」は、薬剤師にとって欠かせない業務のひとつです。
正しい知識と丁寧な対応が、治療効果の向上や服薬アドヒアランスの維持につながります。
この記事では、服薬指導の基礎知識から実際の流れ、患者さん別の対応ポイント、注意点までをわかりやすく解説します。

新人薬剤師の方や、改めて服薬指導を見直したい方にも役立つ内容です。
- 服薬指導の基本的な流れと各ステップで押さえるべきポイント
- 小児、高齢者、外国人など対象別の服薬指導の具体的なアプローチ方法
- 患者さんとの信頼関係を築きながら、服薬アドヒアランスを高める実践的なスキル
薬剤師ポンさんが服薬指導の悩みを解消するための記事を書いてくれました!下記リンク記事もあわせてご覧ください。
▶︎ あわせて読みたい
「服薬指導がうまくできない」を解決!薬剤師ポンさん解説
服薬指導の基礎知識
薬剤師が患者さんに薬の正しい使い方を伝える大切な業務です。
服薬指導とは薬剤師が患者さんに薬の説明をすること
これは薬剤師法第25条の2などの法律によって定められており、薬剤師が必ず行うべき義務の一つとなっています。
🧾 薬剤師法 第25条の2(情報の提供等)
薬剤師は、調剤した薬剤を交付する場合において、
患者等に対し、その適正な使用のために必要な情報の提供及び薬剤の使用に際しての指導を行わなければならない。
服薬指導は単に薬の説明書に書かれている内容を読み上げるだけではありません。
患者さん一人ひとりの病状や生活習慣、これまでの既往歴などを考慮しながら、その方に最適な服薬方法を提案し、薬物治療の安全性と有効性を確保することが目的となります。
薬剤師は処方箋を受け取った瞬間から、患者さんの薬歴を確認し、年齢や体重に適した処方なのか、副作用のリスクはないかなどを客観的に評価します。
そして服薬指導を通じて、患者さんが薬に対して抱く不安や疑問に寄り添い、薬物治療への積極的な参加を促していきます。
服薬指導の目的
服薬指導には主に3つの重要な目的があります。
薬は正しく使用されて初めて期待される効果を発揮します。用法用量を守ることはもちろん、服用のタイミングや食事との関係など、細かな指導によって治療効果を高めることができます。
どんな薬にも副作用のリスクが存在します。服薬指導では、注意すべき副作用の初期症状を患者さん自身が認識できるよう説明し、早期発見・早期対応につなげます。また、飲み合わせの注意点を伝えることで、薬物相互作用による健康被害も防ぐことができます。
患者さんが薬の必要性を理解し、納得した上で服用を続けられるようサポートします。飲み忘れや残薬の発生を防ぎ、患者さんの生活習慣や価値観を尊重しながら、無理なく服薬を継続できる方法を一緒に考えていきます。
服薬アドヒアランスとは、患者さんが医師や薬剤師の指示に従って、薬を正しく服用し続けることです。治療効果を高めるために重要な要素です。
服薬指導の流れ
服薬指導は一連の流れに沿って進められます。各ステップでのポイントを押さえることで、質の高い服薬指導が実現できます。
患者さんに声をかける

処方薬の調剤が完了したら、薬剤師が窓口で患者さんに声をかけ、投薬カウンターへ誘導します。この最初の接点が非常に重要です。
まずはしっかりと患者さんの目を見て、名札を提示しながら「薬剤師の○○です」と自己紹介をしましょう。
些細なことのように思えますが、患者さんとの信頼関係を築くためには第一印象が大切です。明るく丁寧な挨拶を心がけることで、患者さんは「この薬剤師なら安心して相談できる」と感じてくれます。
患者さんの状況に応じた配慮も欠かせません。
足が不自由な方や妊娠中の方には椅子のある場所で指導を行う、耳が不自由な方には筆談の準備をするなど、臨機応変に対応しましょう。患者さん一人ひとりに寄り添う姿勢が、その後のコミュニケーションを円滑にします。
患者さんの病状をヒアリングする
医師の診断を受けた後であっても、薬剤師として独自に情報を集めることで、処方の適切性を確認し、より良い服薬指導を行うことができます。
初回来局の患者さんには、質問票に病状の記載を促し、状況を把握します。特に以下の情報は必ず確認しましょう。
- 現在の症状と程度:どのような症状があり、どの程度困っているのか
- 既往歴とアレルギー歴:過去にかかった病気や薬物アレルギーの有無
- 併用薬の確認:他の医療機関で処方された薬やサプリメント、市販薬の服用状況
- 副作用歴:過去に薬で副作用を経験したことがあるか
- 妊娠・授乳の状況:女性の場合は必ず確認が必要
お薬手帳を確認するだけでなく、口頭でも丁寧に聞き取ることが大切です。お薬手帳にシールを貼り忘れていたり、院内処方薬が記載されていないこともあるためです。
医薬品について説明・指導する
患者さんの状況を把握したら、処方された薬について説明を行います。実際に処方薬を見せながら、錠数と薬剤を患者さんと一緒に確認し、以下の内容を分かりやすく伝えます。
説明すべき主な内容
- 薬の名前と効能・効果
- 用法・用量(1回何錠を、1日何回、いつ服用するか)
- 服用のタイミング(食前、食後、食間など)
- 副作用と初期症状
- 飲み合わせの注意点
- 保管方法
説明する際は、専門用語をできるだけ避け、患者さんが理解しやすい言葉を選びましょう。
例えば「頓服」ではなく「症状がある時に飲む薬」、「服用」ではなく「飲む」といった平易な表現を使うことで、患者さんの理解が深まります。
また、1回2錠服用する薬や、食間・食前など特殊な飲み方をする薬については、特に丁寧に説明し、薬情や薬袋に印をつけるなどの工夫も有効です。
疑問点を確認する

薬の説明が終わったら、必ず患者さんに疑問点がないか確認しましょう。ここで重要なのは、開いた質問(オープン・クエスチョン)を使うことです。
「何か質問はございませんか」「お困りのことはございませんか」といった質問をすることで、それまであまり話をしてくださらなかった患者さんが「実は…」と相談してくれるケースがあります。
「はい」「いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、患者さんが自由に話せる質問形式にすることがポイントです。
患者さんの表情や言動から、理解できているか、不安そうな様子はないかを読み取る観察力も大切です。説明した内容を患者さん自身の言葉で言い直してもらう「ティーチバック法」を活用するのも効果的です。
クロージングを行う
服薬指導の最後には、適切なクロージングを行います。重要なポイントを簡潔にまとめ、次回の来局時期や注意すべき症状があれば医師や薬剤師に連絡するよう伝えます。
「お大事になさってください」という言葉とともに、笑顔で患者さんを送り出しましょう。会計処理も丁寧に行い、レジの打ち間違いや釣銭の間違いがないよう注意します。
会計ミスは患者さんの信頼を損なう原因となるため、慎重に対応しましょう。
服薬指導で説明する主な内容
患者さんが安心して服薬できるよう、正確かつわかりやすく伝えることが大切です。
薬の効能・効果
例えば、高血圧の薬であれば「血圧を下げる薬」というだけでなく、「血圧が高い状態が続くと、心臓や血管に負担がかかり、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。
この薬は血圧を適切な値に保つことで、そうしたリスクを減らすために使われます」と、薬の目的を明確に伝えましょう。
また、薬には複数の効能がある場合もあります。患者さんに処方された薬が、どの症状に対して使われているのかを明確にすることで、患者さんの理解と納得が深まります。
服用方法とタイミング
服用方法とタイミングは、薬の効果を最大限に引き出すための重要なポイントです。
主な服用タイミング
| タイミング | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 食前 | 食事の30分~1時間前 | 糖尿病治療薬など |
| 食直前 | 食事の直前(5~10分前) | 一部の糖尿病治療薬 |
| 食後 | 食事の30分以内 | 多くの内服薬 |
| 食間 | 食事と食事の間(食後2時間程度) | 胃粘膜保護剤など |
| 就寝前 | 寝る30分~1時間前 | 睡眠薬など |
特に「食間」は「食事中」と誤解されやすいため、丁寧に説明しましょう。
また、「1日3回毎食後」という指示でも、患者さんの生活リズムによっては食事回数が異なる場合があります。患者さんの実際の食生活を確認し、必要に応じて医師と相談しながら、無理なく服用できる方法を提案することが大切です。
副作用と飲み合わせの注意点
特に注意すべき副作用の初期症状を具体的に説明し、そうした症状が現れた場合はすぐに医師や薬剤師に相談するよう伝えましょう。
例えば、降圧薬であれば「めまいやふらつきが起こることがあります」、抗生物質であれば「お腹がゆるくなったり、発疹が出たりすることがあります」といった具体的な症状を伝えます。
飲み合わせについても重要な注意点です。
- 薬と薬の飲み合わせ:他の処方薬や市販薬との相互作用
- 薬と食品の飲み合わせ:グレープフルーツジュースと一部の高血圧薬など
- 薬とアルコールの飲み合わせ:睡眠薬や抗不安薬など
これらの情報を分かりやすく説明し、患者さんが安全に薬を使用できるようサポートします。
【患者別】服薬指導の例
患者さんの年齢や状況によって、服薬指導のアプローチは大きく異なります。それぞれの特性に合わせた指導が求められます。
小児の服薬指導では、服薬介助を行う保護者に向けて指導を行うことがほとんどです。保護者の不安に寄り添いながら、子どもが安全かつ確実に服薬できる方法を提案します。
小児
小児服薬指導のポイント
- 服薬介助を行う人の確認:母親なのか、祖父母なのか、保育園に依頼するのかを確認し、その方に合わせた説明を行う
- 過去の服薬経験の確認:嫌がって飲めなかった薬や吐いてしまった経験があれば、詳しく聞き取る
- 剤形に応じた指導:シロップ、粉薬、錠剤など、それぞれの飲ませ方を具体的に説明する
- アレルギーの確認:小児では服薬経験が少なく、アレルギーの有無が不明な場合も多いため注意が必要
年齢別のアプローチ
乳児期(0~1歳)では、粉薬を水で練って頬の内側に塗布する方法や、シロップをスポイトで飲ませる方法を説明します。歯が生えていない時期は味を感じにくい場所に塗布するのがコツです。
幼児期(1~6歳)になると、本人も徐々に理解できるようになります。保護者への指導に加えて、子ども本人を褒めたり励ましたりすることで、前向きな服薬態度を育てることができます。「頑張ったねシール」などのご褒美制度も効果的です。
学童期(6~12歳)では、本人への説明の割合を増やしていきます。薬の必要性や効果を年齢に応じた言葉で説明し、自分で服薬管理できるようサポートしていきます。
高齢者
高齢者の服薬指導では、加齢に伴う身体機能の低下や複数疾患の併存、多剤併用(ポリファーマシー)などを考慮した対応が必要です。
高齢者服薬指導のポイント
- 視力・聴力の低下への配慮:薬袋の文字が読めるか確認し、必要に応じて大きな文字で書き直す。説明が聞き取れているか、患者さんの反応を見ながら声の大きさを調整する
- 服薬管理能力の確認:自分で薬の管理ができるか、服用タイミングを理解できているかを確認する
- ポリファーマシーへの注意:複数の医療機関を受診している場合、同じような作用の薬が重複していないか確認する
- 残薬の確認:飲み忘れや飲み間違いによる残薬がないか確認し、服薬カレンダーの活用や一包化を提案する
一包化とは、複数の薬を服用時間ごとにまとめて1袋に包装する方法です。飲み間違いや飲み忘れを防ぎ、服薬管理を簡単にします。
高齢者では肝機能や腎機能の低下により、薬の代謝や排泄が遅くなり、副作用が出やすくなります。
また、体内の水分量が減少し脂肪の割合が増えるため、脂溶性の薬が体内に蓄積しやすくなります。こうした生理学的変化を踏まえて、副作用の早期発見に努めることが重要です。
認知機能の低下がある場合は、ご家族や介護者と連携し、確実に服薬できる環境を整えることも薬剤師の役割となります。
外国人
外国人患者への服薬指導では、言語の壁や文化・習慣の違いを乗り越えながら、安全で効果的な薬物治療を提供することが求められます。
外国人服薬指導のポイント
- コミュニケーションツールの活用:翻訳アプリ、多言語対応の服薬指導シートや指さしツール、医療通訳サービスなどを活用する
- やさしい日本語の使用:専門用語を避け、短く区切った分かりやすい日本語で説明する
- 視覚的な説明:イラストや実物を見せながら説明することで、言葉が通じなくても理解を促す
- 文化・宗教への配慮:食事制限や服薬に関する宗教的な制約がないか、必要に応じて確認する
外国人患者さんへの対応で大切なのは、「言語が完璧でなくても、コミュニケーションを諦めない」という姿勢です。一生懸命に伝えようとする熱意は、言語の壁を超えて相手に伝わります。
また、外国人患者さんは自己主張をはっきりする文化で育った方も多いため、質問や意見を積極的に聞き出す姿勢も重要です。丁寧に対応することで、安心して治療を受けられる環境を作ることができます。
服薬指導のポイント
質の高い服薬指導を行うためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
患者さんの話を丁寧に聞く
患者さんの話を丁寧に聞くことで、以下のような効果が得られます。
- 隠れた問題の発見:服薬に関する困りごとや、医師には話しにくかった症状などを知ることができる
- 信頼関係の構築:話を真剣に聞いてもらえることで、患者さんは薬剤師を信頼し、相談しやすくなる
- 生活背景の把握:何気ない会話から患者さんの生活環境や食生活が見えてくることがある
傾聴のコツは、患者さんの話を遮らず、相槌を打ちながら最後まで聞くことです。
そして患者さんの意見や価値観を受け入れる姿勢を持つことが大切です。たとえ薬剤師の考えと異なっていても、まずは患者さんの気持ちを理解しようと努めましょう。
専門用語の使用を避ける
薬剤師が当たり前に使っている専門用語は、患者さんにとっては理解しにくいものです。平易な言葉に置き換えて説明することで、患者さんの理解が深まり、信頼関係も築きやすくなります。
専門用語を平易な言葉に置き換える例
- 「頓服」→「症状がある時に飲む薬」
- 「服用」→「飲む」「使う」
- 「嚥下」→「飲み込むこと」
- 「腎機能」→「腎臓の働き」
- 「副作用」→「薬による好ましくない症状」
説明する際は、患者さんの理解度に応じて言葉を選び、専門用語を使う場合は必ず分かりやすく補足説明を加えましょう。
患者さんの生活習慣を考慮する
薬物療法では、患者さんの日常生活における習慣やクセが、治療の成果に大きく影響することがあります。そのため、服薬指導では患者さんの生活習慣を把握し、それに合わせた提案を行うことが重要です。
確認すべき生活習慣
- 食生活:1日の食事回数、食事時間、味付けの好み、コーヒーやお茶の摂取頻度
- 運動習慣:日常的な運動量、通勤方法、趣味の活動
- 睡眠パターン:就寝時間、起床時間、昼寝の有無
- 仕事や家事の状況:勤務時間、シフト勤務の有無、忙しい時間帯
これらの情報を把握することで、患者さんが無理なく服薬を続けられる方法を提案できます。
例えば、朝が忙しい患者さんには前夜に薬を準備する方法を、不規則勤務の方には服薬リマインダーアプリの活用を提案するなど、個々の生活リズムに合わせたサポートができます。
服薬指導をする際の注意点
服薬指導を行う際には、法的・倫理的な注意点や、継続的な自己研鑽の必要性についても理解しておく必要があります。
個人情報の取り扱いに注意する
服薬指導では、患者さんの病状や既往歴、服用薬など、多くの個人情報を扱います。これらの情報は適切に管理し、プライバシーを保護しなければなりません。
個人情報保護のポイント
- 服薬指導の場所への配慮:他の患者さんに会話が聞こえないよう、個室やパーティションのある場所で指導を行う
- 声の大きさへの配慮:必要以上に大きな声で病名や薬の内容を話さない
- 薬歴の厳重管理:薬歴には患者さんの詳細な情報が記載されているため、第三者が見られないよう適切に管理する
- 電話対応の注意:電話での問い合わせには、本人確認を徹底する
特に注意が必要なのは、抗がん剤などセンシティブな薬が処方されている場合です。患者さんががん告知を受けていない可能性も考慮し、慎重に対応する必要があります。
継続的に知識をアップデートする
医療や薬学の知識は日々進歩しています。新しい薬が次々と開発され、既存の薬についても新たな知見が報告されます。薬剤師として質の高い服薬指導を提供し続けるためには、継続的な学習が欠かせません。
知識をアップデートする方法
- 専門誌や学術論文を読む:最新の医療情報や薬物治療のエビデンスを学ぶ
- 研修会や勉強会への参加:他の薬剤師との情報交換や事例検討を通じて学ぶ
- e-ラーニングの活用:時間や場所を選ばず、自分のペースで学習できる
- 症例検討会の実施:実際の症例を通じて実践的な知識を深める
また、患者さんとの対話を通じて新たな気づきを得ることも重要な学習機会です。患者さんの質問や相談から、自分の知識の不足に気づき、学びのきっかけとすることができます。
まとめ
服薬指導は、薬剤師が患者さんに対して行う最も重要な業務の一つです。
単に薬の情報を伝えるだけでなく、患者さん一人ひとりの状況に寄り添い、安全で効果的な薬物治療を実現するために不可欠です。
服薬指導の基本は、患者さんとの丁寧なコミュニケーションです。
患者さんの話をしっかりと聞き、専門用語を避けた分かりやすい説明を心がけ、生活習慣を考慮した提案を行うことで、服薬アドヒアランスの向上につながります。

小児、高齢者、外国人など、患者さんの属性や状況に応じた適切なアプローチを取ることも重要です。それぞれの特性を理解し、柔軟に対応する力が求められます。
個人情報の適切な取り扱いや継続的な知識のアップデートといった注意点を守りながら、患者さんとの信頼関係を築き、質の高い服薬指導を提供していきましょう。
薬剤師の専門性を発揮し、患者さんの健康を守るために、日々の服薬指導に真摯に向き合うことが大切です。
▶︎ あわせて読みたい
“本当に頼れる”転職エージェントおすすめ5社|4回の転職経験をもとに厳選!



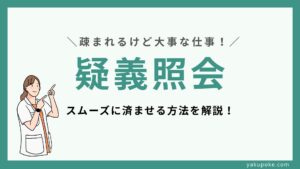
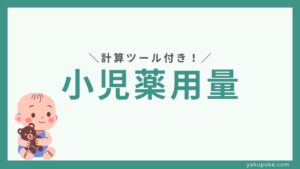
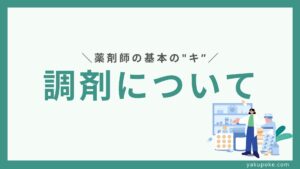
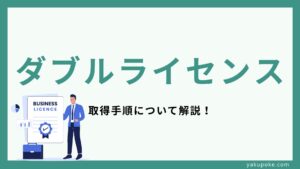
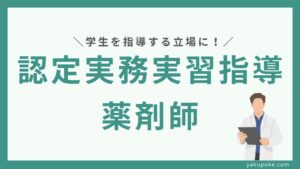

コメント