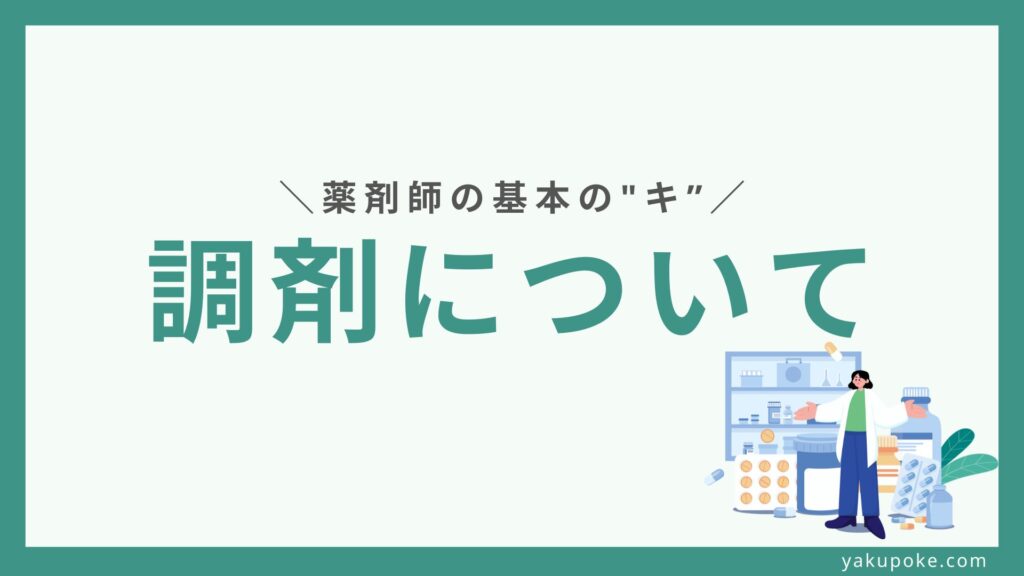
- 調剤薬局とドラッグストアは何が違うんだろう?
- 処方箋を出してから薬をもらうまで、裏側でどんな作業が行われているのか知りたい
- 調剤薬局で働きたいけど、どんな資格や経験が必要?
病院で処方箋をもらったとき、調剤薬局に立ち寄る方は多いでしょう。
実は調剤薬局は、単に薬を受け取る場所ではありません。薬剤師や調剤薬局事務といった専門スタッフが連携しながら、私たちの健康を支える大切な役割を担っています。
適切な調剤は、患者さん一人ひとりの健康維持や生活の質の向上に欠かせない要素です。
- 調剤とはどのような業務なのか、薬が手元に届くまでのプロセス
- 調剤薬局で働くスタッフの種類と、それぞれに必要なスキルや資格
- 薬剤師や調剤薬局事務として働く場合のキャリアの積み方
調剤の基礎知識
薬がどのように患者さんのもとへ届くのか、基本を押さえましょう。
調剤とは処方箋にもとづいて薬剤を調製し、交付する業務
処方箋の内容をしっかりと確認し、適切な薬を選んだ上で、必要に応じて粉砕や混合といった調製を行います。
医師の処方に基づいて正確に薬を調剤することで、医療の質と安全性を高める役割を果たしています。

薬の効果や副作用について説明したり、正しい服用方法をアドバイスしたりする服薬指導も、調剤業務の大切な一部です。
調剤薬局は保険診療の仕組みに基づいて運営されており、「保険薬局」として登録されているところがほとんどです。そのため、患者さんは通常3割の自己負担で薬剤やサービスを受けることができます。
調剤が提供される場所
調剤薬局は、時代のニーズに合わせてさまざまな形で展開されています。それぞれの形態によって、患者さんにとっての利便性や特徴が異なります。
主な調剤薬局の形態
| 形態 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 門前薬局 | 病院やクリニックのすぐ近くに立地 | 受診後すぐに薬を受け取れて便利 |
| 門内薬局 | 病院の敷地内に開設 | 移動距離が少なく、体調が悪いときや高齢の方にも優しい |
| 面分業薬局 | 幅広い医療機関からの処方箋を扱う | 複数の病院にかかっている方の薬を一括管理できる |
| 併設型薬局 | 商業施設やドラッグストアに併設 | 買い物のついでに立ち寄りやすい |

聞きなれない言葉もありますが、調剤薬局での勤務を考えている方は、あらかじめこうした専門用語を理解しておくと、実際の業務でスムーズに対応できます。
「点分業」は、特定の医療機関の処方箋を中心に受け付ける薬局の形態です。受診後すぐに薬を受け取れる便利さがあり、薬局側も取り扱う診療科が限られるため、在庫管理がしやすいというメリットがあります。
一方、「面分業」は、地域のさまざまな医療機関からの処方箋に対応する形態で、“かかりつけ薬局”としての役割を担います。厚生労働省もその普及を推進しており、薬の安全な使用や医療費の適正化といった観点から注目されています。
厚生労働省は「すべての薬局を『かかりつけ薬局』へ」との目標を掲げ、薬剤師による服薬情報の“一元的・継続的把握”など、薬学的管理・指導の強化を通じて、医療費の適正化・薬物療法の安全性向上を推進しています。
調剤薬局とドラッグストアの違い
調剤薬局とドラッグストア、どちらも薬を扱うお店ですが、実は役割や機能に明確な違いがあります。
調剤薬局
処方箋に基づいた医療用医薬品の調剤を中心に行っており、薬剤師が常駐して専門的な服薬指導を提供しています。保険診療の仕組みで運営されているため、医師の処方に従った薬の提供が主な業務となります。
ドラッグストア
本来、調剤を行わずに市販薬や日用品を販売するお店でしたが、最近では薬剤師や保険薬剤師が常駐しているドラッグストアも増えてきました。
こうした併設型ドラッグストアでは、処方箋による調剤と市販薬の販売の両方に対応しているため、医療用医薬品と市販薬を一か所で手に入れられる便利さがあります。
調剤のプロセス
調剤薬局では、患者さんが安全に薬を服用できるよう、厳格な手順に沿って業務を進めています。安全で確実な服薬をサポートするために、次のようなプロセスで保険調剤を行っています。
処方箋の受付
患者さんから処方箋と保険証、お薬手帳を預かり、内容を確認します。
このとき、調剤薬局事務が窓口で対応します。確認項目は以下です。
- 処方箋の有効期限
- 保険証の記号番号
受付の際には、アレルギーや副作用の経験、既往歴や併用中の薬などを把握するため、アンケート(質問票)に記入していただくこともあります。
この情報は、後の疑義照会や服薬指導で大切な役割を果たします。
処方箋は発行日を含めて4日以内が有効期限となっており、期限を過ぎてしまうと調剤を受けることができません。そのため、受付時の確認がとても重要になります。
処方内容の確認と疑義照会
薬剤師は処方箋の内容を細かくチェックします。
- 重複して投与されていないか
- 投与禁忌の薬ではないか
- アレルギーや副作用への配慮がなされているか
処方内容に何か不備がある場合や、確認したいことがある場合には、処方元の医師に問い合わせる(疑義照会)ことが薬剤師法で義務付けられています。これは患者さんの安全を守るための大切な業務であり、薬剤師の専門性が活きる場面でもあります。
薬の調剤と薬剤管理
処方内容の確認が終わると、実際に薬を準備する調剤作業に入ります。
調剤では以下の内容に注意します。
- 調剤には内服薬の取り揃え
- 散剤の計量や混合
- 軟膏の調製
- 注射薬の混合
調剤が終わったら、必ず監査業務を行います。
用意した医薬品が処方箋の内容と間違いなく一致しているか再度確認することで、調剤ミスを防ぎます。

多くの薬局では、調剤した薬剤師とは別の薬剤師が監査を行うダブルチェック体制を取っており、より安全性を高めています
医薬品の管理も大切な業務の一つです。適切な保管環境の維持、有効期限の管理、在庫管理などを通じて、常に品質の高い医薬品を患者さんに提供できる体制を整えています。
服薬指導
単に薬の飲み方を説明するだけでなく、患者さんの症状や悩み、不安を丁寧に聞き取りながら、適切なアドバイスを提供します。
服薬指導では、以下の内容に注意して説明します。
- 薬の名称や効能、効果の説明
- 正しい服用方法(用法・用量、服用時間)
- 保管方法(温度、湿度、光への配慮)
- 服用時の注意点(飲み合わせ、食事との関係)
- 予想される副作用とその対処法
- 薬の効果が現れるまでの期間
患者さんの理解度や生活習慣に合わせて説明方法を工夫することで、服薬アドヒアランス(患者さんが主体的に治療に参加する度合い)の向上につながります。
また、前回処方された薬の効果や副作用の有無を確認することで、継続的な薬物療法をサポートします。
▶︎ あわせて読みたい
服薬指導とは?薬剤師が知っておきたい基礎知識と実践ガイド
薬歴管理とレセプト請求
薬歴には患者さんの基本情報や疾患、アレルギー、これまで服用した薬などを記載し、適切な医薬品の提供や調剤報酬請求の根拠として活用されます。
薬歴管理により、重複投薬や相互作用をチェックでき、副作用歴の確認により安全性が向上します。
また、継続的な服薬指導により治療効果が高まり、複数の医療機関を受診している患者さんの薬を一元管理できるメリットもあります。
レセプト業務は、審査支払機関を通じて健康保険の保険者(協会けんぽ、組合健保、市区町村など)に調剤報酬を請求する業務です。
調剤薬局の収入の元になる大切な業務であり、薬剤師と調剤薬局事務が協力して正確に行います。
レセプト作成には保険や調剤報酬についての専門的な知識が必要で、入力ミスや不備があると審査に影響するため、細心の注意が求められます。
調剤薬局の役割
調剤薬局は単に処方箋に基づいた薬を渡すだけでなく、地域の医療において幅広い役割を担っています。
地域住民の健康維持に関する相談受付
薬剤師は薬の専門家として、処方薬の正しい使い方、副作用や飲み合わせの確認、服薬タイミングの調整など、日常的な相談に対応しています。
また、必要に応じて、薬剤師は症状の重さや薬の副作用などを判断し、医師の受診を勧めることもあります。
状況に応じて、どの診療科を受診すべきか助言するなど、地域住民の健康を守る身近な相談窓口として機能しています。
こうした対応を通じて、薬局は地域住民のセルフメディケーション(自分自身の健康管理)を支える重要な役割を担っています。
患者さんの多角的なサポート
現代の調剤薬局は、単なる調剤業務にとどまらず、患者さんの生活全体を支えるサポート機能を強化しています。
- お薬手帳による服薬履歴の一元管理
- ジェネリック医薬品への切り替え相談による医療費削減支援
- 残薬確認と整理による薬の適正使用の促進
かかりつけ薬局は医薬分業の原点とされ、厚生労働省も患者本位の医薬分業の実現に向けて、調剤薬局のかかりつけ薬局化を後押ししています。
かかりつけ薬局を持つことで、複数の医療機関から処方された薬を一元的に管理でき、重複投薬や相互作用のリスクを減らすことができます。
休日や在宅医療への対応
地域の薬剤師会が中心となって休日当番薬局を設定し、休日でも処方箋に基づいた調剤が受けられる体制を整えています。これにより、急な体調不良や慢性疾患の継続治療において、患者さんの不安を和らげています。
また、高齢化社会が進むにつれて、在宅医療の必要性が高まっています。
調剤薬局でも在宅訪問による服薬指導を実施しており、通院が難しい患者さんの自宅を訪問して、薬の管理や服薬状況の確認、副作用のチェックなどを行っています。

在宅医療では、医師、看護師、介護職員などと連携したチーム医療の一員として、患者さんの生活の質(QOL)向上に貢献しています。
調剤薬局で働く職種
調剤薬局では、主に薬剤師と調剤薬局事務という2つの職種が協力して業務を行っています。それぞれの役割は明確に分かれており、専門性を活かした連携が調剤薬局の円滑な運営を支えています。
薬剤師
薬剤師の主な業務内容には、以下があります。
- 処方箋に基づく医薬品の調製・計量・混合といった調剤業務
- 調剤した薬が処方箋と一致しているか確認する監査業務
- 処方内容に疑問がある場合の医師への問い合わせ(疑義照会)
- 薬の効能や服用方法、副作用などを説明する服薬指導
- 患者さんの服薬履歴の記録と管理を行う薬歴管理
- 在庫管理や品質管理、有効期限の管理といった医薬品管理
処方箋に疑問があれば医師と連携するなど、高度な専門知識と責任が求められます。
調剤薬局事務
会計業務や患者対応を通じて薬剤師をサポートする役割も重要です。
資格が必須ではありませんが、取得することで業務理解が深まり、採用の際に有利になったり、業務の幅が広がったりする利点があります。
調剤薬局事務の主な業務内容は多岐にわたります。
- 処方箋の受付と患者基本情報の確認
- 保険証の確認と情報入力
- レセプトコンピューター(レセコン)への処方内容入力
- 調剤報酬明細書(レセプト)の作成と点検
- 会計業務(薬剤費の計算と領収書発行)
- 電話応対と予約管理
- 医薬品の発注、納品確認、在庫管理の補助
- 薬局内の清掃や整理整頓
- 薬剤師の業務サポート

また、患者さんから処方箋を受け取り、受付業務や問い合わせ対応を行うなど、薬局の顔として患者さんと薬剤師をつなぐ役割を担っています
調剤薬局で求められるスキルと資格
安全で質の高い医療提供のためには、知識とコミュニケーション力が欠かせません。
薬剤師に求められるスキルと資格
薬剤師として働くためには、薬剤師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を取得する必要があります。国家試験の受験資格を得るには、大学の薬学部(6年制)を卒業することが必要です。
さらに、保険薬局で働くには所轄の地方厚生局に申請し、保険薬剤師として登録する必要があります。
求められる主なスキルとしては、以下のとおりです。
- 薬学に関する専門知識
- 医薬品の適正使用に関する判断力
- コミュニケーション能力(患者さん対応、医師との連携)
- 細部への注意力と正確性
- 継続的な学習意欲(新薬情報、医療制度の変更への対応)
- 責任感と倫理観
薬剤師としての専門性を高めるため、実務経験を積んだ後に取得できる認定制度も整備されています。
代表的なものには、一般的な薬物療法を幅広く扱う「認定薬剤師」、特定領域の専門知識を持つ「専門薬剤師」、地域に密着した服薬支援を行う「かかりつけ薬剤師」があります。
調剤薬局事務に求められるスキルと資格
しかし、関連する資格を取得すると、就職時の採用率が上がる、業務内容の理解が深まり即戦力として活躍できる、レセプト作成など専門性の高い業務を任せてもらいやすい、キャリアアップの選択肢が広がるといったメリットがあります。
主な関連資格には次のようなものがあります。
- 調剤事務管理士:調剤報酬請求など、調剤薬局に特化した医療事務知識を認定。
- 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク):病院・クリニックなど幅広い医療機関で活かせる汎用資格。
- 登録販売者:一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できる国家資格。調剤薬局のOTC販売部門でも活躍可能。
OTCとは「Over The Counter」の略で、医師の処方箋がなくても購入できる薬のことを指します。
風邪薬・鎮痛薬・胃腸薬などが代表的です。
求められる主なスキルとしては、コミュニケーション能力(患者さん対応、薬剤師との連携)、正確性(データ入力、会計処理)、PCスキル(レセコン操作、データ管理)、医療保険制度の基礎知識、薬の基本的な知識、マルチタスク能力(複数の業務を同時進行)などが挙げられます。
調剤薬局でのキャリアパス
経験を重ねることで、専門性を高めたり管理職を目指す道もあります。
薬剤師としてのキャリア
新人薬剤師(1年目~2年目)の時期は、調剤業務や服薬指導の基本スキルの習得に集中します。処方箋の読み方、調剤の基本技術、患者さんとのコミュニケーション方法などを学びます。
中堅薬剤師(3年目~5年目)になると、在宅医療や健康相談などの専門的なサービスも担当するようになり、地域医療に深く関わっていきます。
ベテラン薬剤師(5年目以降)は、後輩の育成や店舗運営にも携わるようになり、経験を積むことで複数店舗の統括や経営層への道も開かれます。
管理薬剤師は、薬機法で医薬品を取り扱う薬局・店舗への配置が義務化されている責任者で、5年以上の実務経験を持つことが望ましいとされています。
従業員の監督と指導、医薬品の品質管理と在庫管理、薬局運営に関する意思決定、行政対応と薬局開設者への報告などを担当します。

さらに、エリアマネージャーとして担当エリアの複数店舗を管理したり、認定薬剤師・専門薬剤師として特定の分野で高い専門性を発揮したり、十分な経験と資金を用意して自分の調剤薬局を開業したりする道もあります。
調剤薬局事務としてのキャリア
新人事務員(1年目~2年目)は、受付業務、データ入力、会計処理などの基本的な事務作業を学びます。
ベテラン事務員(3年目以降)になると、レセプト業務の全体を任されたり、後輩の教育を担当したりするようになります。
主任・リーダーとして、複数の事務員をまとめる役割を担い、シフト管理や業務分担の調整、新人教育の計画立案などを行うこともあります。
また、調剤薬局事務の経験を活かして、他の医療機関の医療事務や、製薬会社の営業サポート、医療系の事務職など、医療業界内でのキャリアチェンジも可能です。
まとめ
調剤薬局は、処方箋に基づいた薬の調剤を行うだけでなく、地域住民の健康を守る重要な拠点として機能しています。
薬剤師と調剤薬局事務が連携しながら、処方箋の受付 → 疑義照会 → 調剤 → 服薬指導 → 薬歴管理まで、厳格なプロセスに従って業務を遂行しています。
薬剤師として働くには国家資格が必須ですが、調剤薬局事務は資格がなくても始められる職種です。どちらの職種も継続的な学習と経験の積み重ねによって、管理職や専門職としてキャリアアップの道が開かれています。
調剤薬局の役割は、医薬分業の進展とともに広がり続けています。在宅医療への対応やかかりつけ薬局としての機能強化など、地域医療における調剤薬局の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。
医療や薬に関心がある方にとって、調剤薬局での仕事は、人々の健康を支えるやりがいのある選択肢となります。
転職を考えている方へ
もし「医療の現場で人の役に立ちたい」「安定した職場で長く働きたい」と考えているなら、調剤薬局での仕事は非常におすすめです。

薬剤師はもちろん、調剤薬局事務としても未経験から挑戦できる求人が数多くあります。
自分に合った職場を見つけるためには、医療・薬局業界に特化した転職サイトを活用するのがおすすめです。
業務内容・職場環境・教育体制を比較しながら、あなたにぴったりの薬局を見つけてみましょう。
▶︎ あわせて読みたい
“本当に頼れる”転職エージェントおすすめ5社|4回の転職経験をもとに厳選!



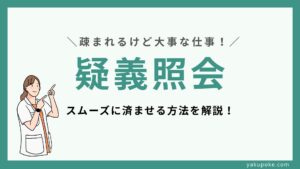
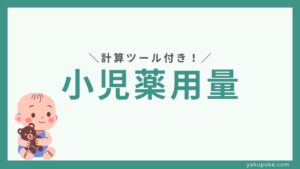
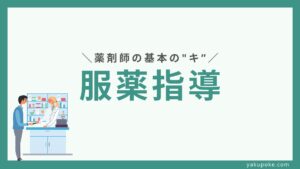
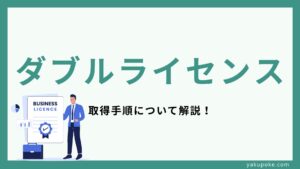
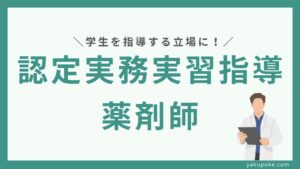

コメント